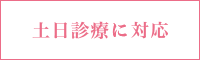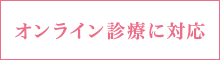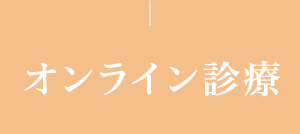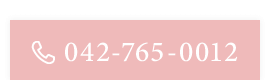「いぼ」とは
 「いぼ」は皮膚が盛り上がったできものを俗称したもので、大きく分けるとウイルス感染性のもとの、体質性のものの2種類があります。
「いぼ」は皮膚が盛り上がったできものを俗称したもので、大きく分けるとウイルス感染性のもとの、体質性のものの2種類があります。
ウイルス感染が原因のいぼ
「いぼ」はウイルスが原因でできるものが多く、ウイルス性のものは「尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい)」や「水いぼ」などが挙げられます。これらは原因となるウイルスが異なるため、治療法も異なります。
尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい)
尋常性疣贅はヒトパピローマウイルスが感染することで発症する「いぼ」で、白色の半球形の数ミリ〜1㎝のものができます。この場合にできる「いぼ」は小さく、自覚症状もない場合が多いです。
水いぼ
「水いぼ」は伝染性軟属腫ウイルスに感染することで発症する「いぼ」で、表面がつるっとして水ぶくれに似ています。大きさは数ミリ~5mmほどになります。
3〜15歳の子どもに多くみられ、手足、脇、股などにできることが多いです。毛を介して感染することが多く、学校の水泳プール場やタオルを共有したりすることで、体毛のある部位に感染することが多いです。
痛みやかゆみなどは少ないのですが、気になって掻きむしってしまうとウイルスが周囲に広がり、増殖するため他人に感染する可能性があります。
半年~3年ほどで自然治癒するものではありますが、見た目や感染防止のために治療を選択されるご家庭が多いです。
治療は専用のピンセットで「いぼ」を切除しますが、当院では痛みを抑えるために患部に麻酔テープを貼り、1時間ほど経ったタイミングで処置します。
青年性扁平疣贅(せいねんせいへんぺいゆうぜい)
青年性扁平疣贅はヒトパピローマウイルスに感染することで発症する「いぼ」で、やや褐色の平たく盛り上がった「いぼ」が線状に広がります。名前の通り、青年期によく発症するもので、特に女性に多く見られます。
痛みやかゆみが伴い、掻きむしってしまうといぼがぴったりくっついてしまったり、新しいいぼができたりすため注意が必要です。
自然治癒するものではありますが、数年の時間を要するので病院での治療を選択する方が多いです。治療法としては漢方のヨクイニン内服や液体窒素で凝固して切除する方法があり、患者様の状態や症状に合わせて適切な治療を行います。
帯状疱疹
 帯状疱疹はヘルペスウイルスの一種である水疱帯状疱疹ウイルスが感染することで起こるもので、水ぼうそうや水痘ワクチンを打った方の神経節にはこのウイルスが存在しています。 健康で免疫が正常の場合には特に症状などはありませんが、ストレスや体調不良により免疫が弱ったタイミングで活性化し、帯状疱疹を発症します。他にも加齢により身体そのものが衰えた方にもよくみられます。 主な症状としては、身体の左右一方に少し痛みを感じるようになり、2日ほどすると赤く小さな水ぶくれができ、神経に剃って帯状に広がります。頭部から足先のどこにでもあらわれ、神経にダメージを与えるので、治癒しても神経痛が残る可能性があります。
帯状疱疹はヘルペスウイルスの一種である水疱帯状疱疹ウイルスが感染することで起こるもので、水ぼうそうや水痘ワクチンを打った方の神経節にはこのウイルスが存在しています。 健康で免疫が正常の場合には特に症状などはありませんが、ストレスや体調不良により免疫が弱ったタイミングで活性化し、帯状疱疹を発症します。他にも加齢により身体そのものが衰えた方にもよくみられます。 主な症状としては、身体の左右一方に少し痛みを感じるようになり、2日ほどすると赤く小さな水ぶくれができ、神経に剃って帯状に広がります。頭部から足先のどこにでもあらわれ、神経にダメージを与えるので、治癒しても神経痛が残る可能性があります。
帯状疱疹後神経痛について
帯状疱疹は放置していると治癒したとしても神経痛が残り、悪化した場合には日常生活に支障が出るほどの痛みが生じるようになります。これ症状を「帯状疱疹神経痛」と言います。ウイルスによって神経が傷つく事が原因で、炎症によるダメージと違って神経からくる痛みの為、強い痛みを伴います。
当院の治療
治療の基本は抗ウイルス剤の内服による薬物療法で、ファムビル🄬(ファムシクロビル錠)やバルトレックス🄬(バラシクロビル塩酸塩)、アメナリーフ🄬(アメナメビル錠)などがあります。服用頻度に違いはありますが、どれもウイルス増殖を抑える優れた効果を期待でき、飲み始めから1週間ほどで効果を実感できるようになります。また、痛みやかゆみがひどい場合は塗り薬や痛み止めを併用することもあります。
帯状疱疹の予防接種
帯状疱疹予防接種は、帯状疱疹の発症や、重症化の予防、合併症の予防をすることができます。
ワクチンは2種類あり、接種方法・効果・その持続期間・副反応などの特徴が異なっていますが、いずれのワクチンも帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。
| 生ワクチン (ビゲン) | 組み換えワクチン (シングリックス) | ||
|---|---|---|---|
| 接種回数(接種方法) | 1回(皮下に接種) | 2回(筋肉内に接種) | |
| 接種スケジュール | ― (他の生ワクチン接種から27日以上間隔をあけてください) |
2カ月以上の間隔を置いて2回接種 ※病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1ヶ月まで短縮できます |
|
| 接種できない方 | 病気や治療によって、免疫が低下している方は接種できません。 | 免疫の状態にかかわらず接種可能です。 | |
| 接種に注意が必要な方 | 輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3カ月以上、 大量ガンバグロブリン療法を受けた方は治療後6ヶ月以上置いて接種してください。 |
筋肉内に接種をするため、血小板減少症や凝固障害を有する方、 抗凝固療法を実施されている方は注意が必要です。 |
|
| ワクチンの効果 | 接種後 1年時点 |
6割程度の予防効果 | 9割以上の予防効果 |
| 接種後5年時点 | 4割程度の予防効果 | 9割以上の予防効果 | |
| 接種後 10年時点 |
― | 7割以上の予防効果 | |
| 主な副反応の発現割合 | 70%以上 | ― | 疼痛* |
| 30%以上 | 発赤* | 発赤、筋肉痛、疲労 | |
| 10%以上 | そう痒感*、熱感*、疼痛*、硬結* | 頭痛、腫脹*、悪寒、発熱、胃腸症状 | |
| 1%以上 | 発疹、倦怠感 | そう痒感*、倦怠感、その他の疼痛 | |
*:ワクチンを接種した部位の症状
参照:厚生労働省のHP
当院ではどちらのワクチンもお選びいただけますが準備に時間を要しますので、接種ご希望の場合は必ず事前にクリニックまでお電話にてご相談ください。
令和7年度から65歳以上の方などを対象に、帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まりました。
詳しくはこちらから↓
50歳以上の方、18歳以上で帯状疱疹の罹患リスクの高い方も、定期接種を待たずに予防接種を受けることが可能です。
詳しくはこちらから↓
口唇ヘルペス
口唇ヘルペスの原因
 ヘルペスは単純ヘルペスウイルスの感染が原因で起こるもので、唇や周辺部の粘膜に感染して起こるものを「口唇ヘルペス」と言います。直接肌が触れる以外にも、共有の食器やタオルなど介して感染することもあり、家族間での感染が多く報告されています。一度症状が治癒してもストレスや疲れたまり、免疫力が低下すると症状があらわれ、症状の改善と発症を繰り返します。
ヘルペスは単純ヘルペスウイルスの感染が原因で起こるもので、唇や周辺部の粘膜に感染して起こるものを「口唇ヘルペス」と言います。直接肌が触れる以外にも、共有の食器やタオルなど介して感染することもあり、家族間での感染が多く報告されています。一度症状が治癒してもストレスや疲れたまり、免疫力が低下すると症状があらわれ、症状の改善と発症を繰り返します。
口唇ヘルペスの症状
唇やその周辺部に違和感やチクチクした痛みを伴う赤みが生じる、水ぶくれなどがあらわれます。他にも、口内や耳、首、鼻の下、指などにも症状がでることがあります。
口唇ヘルペスの検査
特別な検査を行う必要はありません。人にうつる可能性があるため、症状にお気づきの際はお早めに当院までご相談ください。
口唇ヘルペスの治療法
治療法はファムシクロビル、アシクロビル、バラシクロビルなどの抗ウイルス薬の内服薬を基本とし、5日間服用して頂きます。
抗ウイルス薬はウイルスの増殖を抑える効果があるので、飲み始めるタイミングとしては、ヘルペスの症状が出たらできる限り早く飲むようにしましょう。
治癒後もウイルスが増加して再発することもあるので、ヒリヒリするなど再発の予兆を感じたらすぐに病院にかかり、早い段階で抗ウイルス薬を飲むようにしましょう。
また、ウイルスは症状が完治後も体に残るので、再発予防のためにもしっかり睡眠をとり、ストレスをかけないような生活を送るようにしましょう。